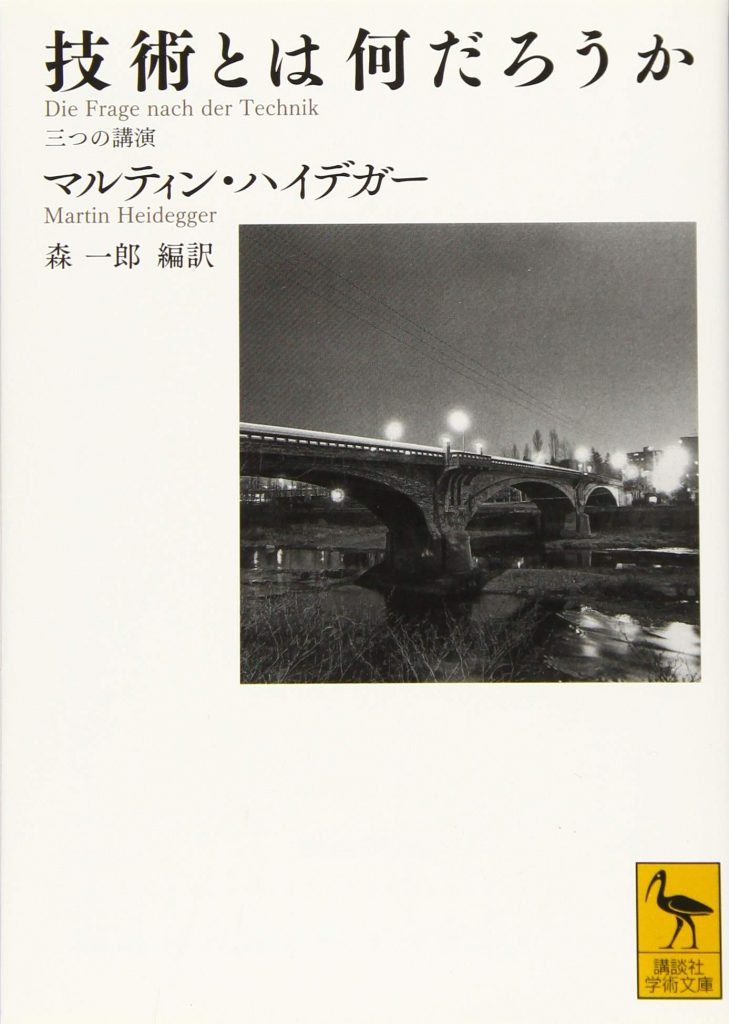
ハイデガーの技術論の、新しい翻訳です。新しいと言っても、この本自体は2019年に出版されています。以前に平凡社ライブラリーから出ている『技術への問い』は読んだことがありましたが、こちらは日本語がかなりわかりやすく、大幅に読みやすくなっている気がします。かといって、訳者も言う通り「超訳」されているわけではなく、内容は普通に難しいです。
技術者として面白かったのは、因果の四原因について具体的に解説している箇所です。四原因とは物事が起こる原因を「質料因」「形相因」「目的因」「作用因」の4つに分類する考え方です。大学の論理学の講義などでは、現在では「作用因」だけを考えればよく、特に「目的因」などというものは原因に含めないと教わるのですが、であればなぜ昔のギリシア人が目的因なるものを考えだしたのか不思議でした。ハイデガーによる具体例を聞くと納得できます。少し長くなりますが引用します。
銀は、それをもとに銀の皿が製造される原料です。銀は、このような素材(ヒュレー〔hylē〕)として、皿に関して、ともに責めを負っています。それをもとに皿が成り立っている原料が、皿にもたらされるのは、銀が責めを負うからであり、つまり銀のおかげです。しかし、お供え用の器具を引き起こした責めを負うのは、銀だけにとどまりません。銀が責めを負うことで引き起こされた当のものが、皿として現れるのは、皿という姿かたちにおいてであり、ブローチや指輪という姿かたちにおいてではありません。つまり、お供え用の器具は、皿らしいものの姿かたち(エイドス〔eidos〕)が同時に責めを負うことで引き起こされるのです。銀は、皿という姿かたちがそこに放ち入れられる原料であり、姿かたちは、銀色のものがそのように現れる形態であり、この両者が、それぞれの仕方で、お供え用の器具に関して、ともに責めを負っているのです。
しかしながら、お供え用の器具に関して、ともに責めを負っているものとしては、とりわけ三番目の要因がまだ残っています。これは、皿を予め限定して、奉納と供物の領域に配する要因です。これによって、その皿は限定されて、お供え用の器具という協会に囲われます。境界を限定するものは、物を終わらせます。この終わりでもって、ものは終止するのではなく、この終わりのほうから、物は、制作後にはできあがった完成品として始まるのです。この意味で終わらせるもの、完成させるもののことを、ギリシア語でテロス〔telos〕と言います。この語は、「目標」や「目的」と翻訳されることがあまりに多かったため、誤解されています。テロスは、お供え用の器具を引き起こした責めをともに負う素材および姿かたちを、引き起こした責めを負うのです。
つまり物事が引き起こされるからには人称的な主体が関わっているというようなケースが主に想定されていたのだと思います。これをWeb開発に置き換えると以下のように考えることができるのではないかと思います。
- 質料因: インターネットのプロトコル、データベース、Webサーバー、Linux、TypeScript、ブラウザ、など。
- 形相因: ブラウザとインターネットを使って使用できるアプリケーション。ブラウザから画面操作を行うことでショッピングができる。
- 目的因: 実店舗に行くことなく、自宅にいながらにしてショッピングができるようにしたい。
このように対置していみると、それぞれが綺麗に「質料因=技術選定」、「形相因=基本設計」、「目的因=要件定義」に対応していることがわかります。そこから先の詳細設計、実装、テスト、受け入れなどのレイヤーは残る一つの「作用因」にまとめることができそうです。
目的因はソフトウェア開発において最上流に位置するものだと考えることができます。それもそのはずで、ハイデガーの解説によれば「目的因」が示しているものは「目的」ではなくて「終わり」だからです。ソフトウェアをその最終形から考えれば、何を作るべきなのかが見えてきます。
形相因はどのような形で実現するかであり、基本設計だとか外部設計と言われる工程にあたると思われます。
質料因は何を使って実現するかであり、技術選定や技術検証と言われる工程にあたるのではないかと思います。
単にAが原因でBが起こった、というような純粋な因果関係のみを論じるのであれば作用因しか必要ありません。人を沢山投入したからソフトウェアが完成した、というような言い方しかできません。しかし前近代的な四原因説に敢えて戻って考えてみると意外にももっと複雑な背景が見えてくるかもしれません。そんなに人を投入しなければならない理由は何だったのか。バグを生みやすい言語を使っているから? そもそも設計に問題があったから? 要件定義があいまいで無駄な機能を実装してしまったから?
ハイデガーのこの本についてはもう少し書きたいことがあるので、次の記事でも別の点について書いてみようと思います。

